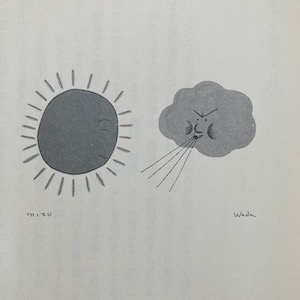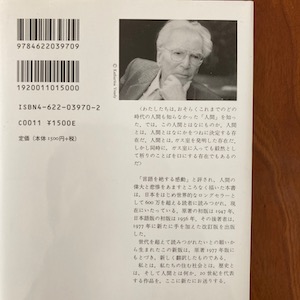塩野七生さんの『男たちへ』のようなコラムを書きませんか、と言われたことがある。もう二十年近く前の話だ。駆け出しのフリーライターにとって原稿の依頼は何でもありがたい。しかし、実際にその本を手に取ってみて大いに困惑した。「フツウの男をフツウでない男にするための54章」というのがそのサブタイトルで、言ってみれば男性論。二十代前半の小娘の書く男性論を、読みたいですか? 私はあんまり、読みたいと思わないなあ。
なんて思ったことを正直に言っていたのでは仕事にならない。代替案にごにょごにょと言い訳を添えて、なんとかその場を凌いだ(どんな代替案だったかは忘れてしまった)。
相手は当時の私よりは年上の、しかし今の私よりは若い女性編集者だった。明確な意図があってというよりは、たまたまそういう企画を思いついたときに、たまたま私が目に留まったんだろう。今となっては「なぜ私に?」というあのときの疑問に明確な答えがないことくらいは承知している。ただ、年齢を言い訳の筆頭に挙げたことを思い出すと、では二十年近く経った今なら男性論が書けるのか、どうなんだろうかと、つい考えてしまう。
私は、テレビ・ニュースを見ているとき、アメリカとソ連の戦力削減交渉の場が写し出されると、ひどく熱心に見たものだった。(中略)その場にいたアメリカの首席代表の、エミッツだったか、まあそんなふうな名の男だったが、ついこの間まで首席をつとめていたその男が、大好きだったからである。
年齢は、八十歳を越えているのだそうだ。だけど、ステキな男だった。眼がいい。じっと相手の眼をみつめて、動かない。
また、話し方がいい。静かで落ちついた話し方をする。それも、抑えた声で。
そして、最もイイ点は、笑い顔を安売りしないことだった。笑い顔を安売りする男には、政治家であろうと財界人であろうと、また俳優であろうと、私は食傷気味なのです。
この人を笑わせてみたい、と私などは思う。八十歳だろうが、そんなことはまったく関係ない。(「第43章 男が上手に年をとるために」より)
男の色気について。男のロマンについて。不幸な男について。成功する男について。独断も偏見も上等、爽快な男性論だ。大著『ローマ人の物語』をものした人だから、マキャベリやダヴィンチといった歴史上の人物も登場するけれども、私はどちらかというと、テレビに映る政治家とか少女時代からファンだった映画俳優を俎上に載せて、その魅力をダーッと語るくだりが好きだ。妙な説得力がある。
でも、「フツウの男」にはあまり参考にならないかもしれないなあ、とも思う(もちろん、別に参考にしなくても読んでおもしろければ十分だけど)。日本の社会で「フツウの男」と言えば、まず会社員だろう。著者の好みを要約すると「スタイルのある男」ということになる。自分のスタイルというものを醸している会社員を、私はうまくイメージすることができないのだ。
スタイルがあるとはどういうことか。本書によると、第一に「年齢、性別、社会的地位、経済状態などから、完全に自由であること」。第二に「倫理、常識などからも自由であること」。以下は省略するけれども、やっぱり会社員には、なかなか難しいのではないか?
私の見知った人で、当てはまるとすれば、転職して最初に入った会社のO専務かもしれない。大手出版社で編集長を勤めあげた後、複数の子会社で役員をしていた人で、私は下っ端の事務員として伝票を作って専務(と社長)にハンコをもらっていた。同じような業務をその後いくつかの会社ですることになったけれども、一番仕事がしやすかったのは間違いなくO専務だ。
月に何度かある「ハンコ押し」のタイミングを把握していて、出張や休暇の予定が決まると「○日から○日までいないよ?」と念押ししてくれる。ほとんど流れ作業のようにハンコを押しながら、たまに発生するイレギュラーな伝票では手を止めて「これ何?」と聞いてくる。世間話や冗談で適度にコミュニケーションをとりつつ、馴れあう隙は見せない。人目を引く美男ではないがポロシャツやダッフルコートがよく似合っていた。
O専務を「スタイルのある会社員(会社役員)」のモデルとして仮定すると、その条件とはどんなものだろうか。塩野先生に倣って、独断と偏見で書き出してみると……。
第一に、自分の価値観と他人の価値観の区別がつくこと。この区別がつかない人には、会社の人間関係が一種のロールプレイであることを理解できない。いわゆるパワハラとかセクハラも、根っこにあるのは価値観の押し付けなんじゃないだろうか。
第二に、わからないことをわからないと言えること。これができないと、不確かな認識に基づいて不確かな判断を下すことになる。年齢や役職に反比例して、できなくなっていく人が多いようだ。
第三に、自分の属している会社を適度に好きでいること。O専務の場合、たとえば私が親会社のことを褒めると(書類を返してくれるのが早いとか、担当者が親切だとか)、親戚の子どもを褒められたみたいにはにかむ。愛社精神というものは、ほとばしるよりは滲みでるくらいがちょうど良いと思う。
……しかしまあ、これでは男性論にならない。強いて言えば会社員論か。若かりし日に「男性論を書け」との依頼に正面から取り組めなかったのは、年齢の問題ではなく、やっぱり資質の問題だったんだな。情けない言い訳をしてしまったものだと、いまさらながら恥ずかしい。