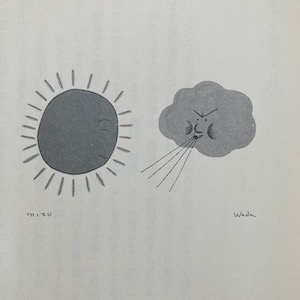フリーライターをしていた頃、私の書いたものを読んで「小説を書いたら」と言う人がたまにいた。そういう人はおそらく小説という形式を文章表現の最上位と捉えていて、「あなたにはそれが書けるよ」という褒め言葉として言ってくれたんだと思う。それを真に受けて小説を書いたり、どこかの編集部に持ち込もうとか新人賞に応募しようとか、そういう野心も余裕も私にはなかった。それに、小説だろうとエッセイだろうと、日記だろうと何だろうと、おもしろいものはおもしろいし、つまらないものはつまらない。形式は別は何でもいいじゃないかと思っていた。
だから、ある文芸誌で小説家ではない人に小説を書かせる特集を組むとのことで依頼が来たときは、いつものクセで深く考えず引き受けてしまった。結果は散々で、小説を書こう、小説にしようと思って手を加えれば加えるほど、そこから遠ざかっていくように感じた。
当時は依頼があれば大概引き受けた、自分に書けるか書けないかなんていちいち考えなかったから、出来のいい原稿もあれば不出来な原稿もある。それはもう、そういう仕事なんだと割り切っていた。でもあの原稿だけは、今でも、思い出せば原稿料をもらったことが恥ずかしくなる。
小説って、何なんだろうなあ。
村上春樹さんがジャズについて書いたエッセイを読んだときも、そんなことを考えるともなく考えた。和田誠さんと一緒に選曲したコンピレーションCDのライナーノーツに掲載されていたエッセイで、CDは人の家に置いてきてしまって手元にないけれども、文庫本『雑文集』にほぼ同じ文章が収められている。
ジャズってどんな音楽ですか、という質問への答えを探す形で、ジャズバーを経営していた頃の思い出が綴られていく。店には基地のアメリカ兵がたまにやってきた。そのなかの一人は何度かビリー・ホリデイをリクエストした。彼は日本人の女性と一緒で、二人は友達とも恋人ともわからない、見ていて気持ちの良い距離感で酒を飲んでいた。
僕は今でも、ビリー・ホリデイの歌を聴くたびに、あの物静かな黒人兵のことをよく思い出す。遠く離れた土地のことを思いながら、カウンターの端っこで声を出さずにすすり泣いていた男のことを。その前で静かに融けていったオンザロックの氷のことを。それから、遠くに去っていった彼のためにビリー・ホリデイのレコードを聴きに来てくれた女性のことを。彼女のレインコートの匂いを。そして必要以上に若くて、必要以上に内気で、そのくせ恐れというものを知らず、人の心に何かを届かせるための正しい言葉をどうしても見つけることができなかった、ほとんどどうしようもない僕自身のことを。(「ビリー・ホリデイの話」より)
そして「こういうことがジャズなんだ、そうとしか答えられない」と締めくくる。
このエッセイから(もしくはジャズという音楽から)、孤独という言葉を連想するのは私だけだろうか? 孤独という言葉を使わずに孤独を表している、少なくとも私はそう感じた。
昔お世話になっていた先生は、小説と批評の違いについてこんなことを言っていた、「的を射抜くのが批評。小説は、読者に的を射させないといけない」と。このエッセイは、まさに読者に(私に)孤独という的を射させている(もちろん的外れの可能性もあるけど、とりあえず的は的だ)。そして、これは小説ではない。だからつい考えてしまうのだ、小説って何なんだろうなあと。
『雑文集』にはエッセイのほかにも、受賞の挨拶とか結婚式の祝電、他の作家の文庫に寄せた解説など、さまざまな文章が掲載されている。わりとどれも、正直さを感じさせる文章だ。村上春樹さんのいくつかの長編小説と比較してみると、もしかすると小説って「正直な人がなるべく正直に書いた作り話」なのかもしれないなあと思う。
とりとめのない思いつき、検証しようのない仮説だ。でも、あのとき(あの恥ずかしい原稿を書いてしまったとき)のことを思い出すと、どうせ小説なんて書けやしないんだから、小説じゃなくてもいいからせめて、もう少し正直に書けばよかった、とは思う。