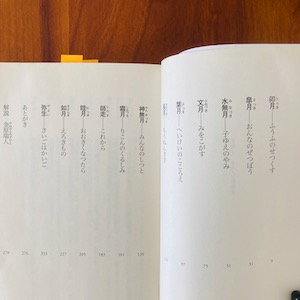兄や姉と一緒に『ルパン三世』の再放送を見ていた頃、オープニングソングで「お~とこには~じぶんの~セェカァイがぁある!」というBメロに差し掛かると、子ども心に「女にはないのかなあ」と思ったものだった。二十代になると、カラオケで『男の勲章』を熱唱する先輩に「女の勲章って何だと思います?」と絡んだりもした。
男の美学を歌った歌はあるけれども、女の美学を歌った歌はない(私が知らないだけかもしれないが)。「男の隠れ家」という雑誌はあるけど、「女の隠れ家」という雑誌はない。塩野七生さんのエッセイにも、「男のロマンという言葉があるけれども、同じことを女がやると、どういうわけかロマンにならない」と書いてあった。
「女の◯◯」の◯◯に当てはめて、しっくりくる言葉ってなんだろうかと、漠然とした疑問を抱えて生きてきたからだろうか。本屋で『女の絶望』という文庫本を目にしたときは、「まさか」という気持ちと「もしかして」という気持ちが入り混じって、中身を確認せずにはいられなかった。
一頁目には「出囃子/カルメン前奏曲」の文字。「ええ、いっぱいのお運びでありがとうございます」という寄席風の口上。語り手は「伊藤しろみ」、地元の新聞で身の上相談の回答を書いている。毎週さまざまな相談が寄せられるが、海千山千を自負する「しろみさん」には、やはり女性からの相談が多い。夫婦の悩み、育児の悩み、セックスの悩み、不倫、更年期、親の介護……。
結婚して四十年になる妻だった。夫は家庭的で、暴力もなく、浮気もせず、稼ぎもまあまあ、でも妻には、目に見えない不満がふつふつとたまっていた。
「休日など二人でどこかへ出かけて、疲れて帰ってきたときに、自分が立ち上がってお茶を入れる奴隷根性に絶望しています。それをごくあたりまえの事のようにのほほんとしている夫のことも憎らしくてたまりません」
ね、ここですよ。絶望、と。
この言葉だ、見つけたと思った。
女の、女たちの、悩みを、不満を、不安を、しとつに集めて表現する言葉。
ずっといいたかったンだが、心ン中から出てこなくて、ずっともやもやしていた言葉だ。(「皐月─おんなのぜつぼう」より)
「人」にわざわざ「しと」と江戸弁のルビをふり、オチには駄洒落を添える。詩人の肩書きを持つ著者が、言葉のテクニックを駆使して「女の絶望」を、軽く、軽く、ころがしていく。あまりに軽すぎて、数年前に手に取ったときは内容が頭に残らなかった。文章が上手すぎて残らない、そんなバカなことがあるだろうかと、不思議に思ったものだった。
著者の伊藤比呂美さんは実際に、西日本新聞で「比呂美の万事OK」という人生相談を担当している。長寿連載で同名の単行本もあるが、あとがきによると本書はあくまでもフィクション。「伊藤しろみ」は「伊藤比呂美」ではなく、悩む人々もその他の登場人物も、架空の存在だという。
しかしながら、心配のあまり「しろみさん」が直接電話をかけた女性が数年後、講演会に手作りのお弁当を差し入れしてくれたとか、回答欄で自分の苦境をグチると、手紙に二千円のお見舞金を同封してきた読者がいたとか。時には「ハッキリ言えば傷つけてしまうかもしれないなあ」とためらったり、「きれいごといってんじゃねえよ」と自分で自分に突っ込んだり。どうも、まったくのフィクションとは思えない。
ここに登場する女たちに、「自分が女でなければ、と思ったことがありますか」と質問したら、たぶん全員「イエス」と答えると思う。生理で下着や服やシーツを汚してしまったとき。痴漢に遭ったとき。差別的な職場や家庭に身を置いているとき。人間関係がこじれたとき。男になりたいとか、男に生まれたかったと思うのではなく、「女でなければ」と思ってしまう。自分で自分の性を呪ってしまう。この世にはたしかに「女の絶望」と言って然るべきものがあるようなのだ。
「一抹の実を核につくった架空の存在、あるいは夢のまた夢。夢から醒めれば、ここに、しとりの、五十過ぎの、疲れたおばさんが、佇んでおります。あたくしです」──新聞の連載では採用できなかった手紙が、たくさんあったに違いない。あの手紙は忘れられない、あの手紙にも答えたかった。いや、回答するのではなく、一緒に悩んだり文句を言ったり、笑い合ったりしたい。……数年ぶりに再読してみると、技巧的な文章の根っこには、そういう汲めども尽きぬ思いが湧いて流れているように感じる。
こんなに丁寧に転がしてもらえるなら、絶望も、悪くないかもなあ。勲章とか、ロマンとか、美学も隠れ家も、私は別に要らないや。