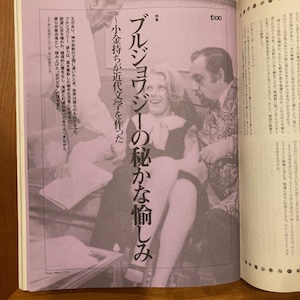
あなたはもうプロなんだから、一円にもならない文章を書いてはいけない。F先生にはいろんなことを教わった、これもその一つだ。もちろんメールや手紙の類はその限りではない、作品としての文章を趣味で書くようになったら、物書きとしておしまいだということ。甲斐のない話になってしまうけれども、一度だけこの教えを破ったことがある。
去年の夏、学生時代の友人と小説を書いて読み合おうということになった。二人ともF先生の下で小説を書くゼミに在籍していた、その思い出話をしていたときのことだった。
フリーライターという少々ヤクザな商売をしている私と違って、彼女はきちんとした勤め人だ。作家に転身するしないは私の関知するところではないが、いつかまた小説を書く意志があるらしいことは薄々知っていた。私自身は、ちょうど書いてみたい題材があった。あるときあるきっかけで感じたコトを、小説という形に仕立ててみたい。どの程度具体的な構想だったか、漠然とした情熱だったかはわからない。別のものを別の眼差しで見ているに違いない友人への共感が、私の口を滑らせた。
「やろう」
〆切りは一ヶ月後、枚数は自由に。いまさら「口を滑らせた」などと言うのは彼女に対して失礼かもしれないが、口が滑りでもしなければ言うこともなかった。後からF先生の教えを思い出して「しまった」と思ったものの、会社員としての生活と経験を数年分重ねた彼女が、どんな小説を書いてくるか。真摯でしばしばユーモラスな評者であった彼女が、今また私の書いたものにどんな言葉を与えてくれるか。約束を交わすと、俄然愉しみになった。
愉しみを覚えたあの瞬間、私は、書くという自分の仕事を趣味に貶めたのだろうか? わかっていたのは、学生同士ではなくなった現在、そのような機会を持つことが、彼女との関係をどのようにか変質させるかもしれないということだった。書くこと、読むことへの真剣さのさじ加減によっては、片方が片方に、あるいはお互いに、幻滅することもあり得る。何が得られるかもはっきりしないのに、私は代えの利かない友人を言わば賭け金にした。
仕事で原稿をやりとりするときの緊張感は、その種類や相手によってさまざまで、単純に比較することはできない。しかし小説だろうと何だろうと、学生だろうとプロだろうと、文章を書くことは大体においていつも何かの賭けだった。何度か、ここぞという時には自分にとってなるべく大きなものを賭けようとしてきた。勝ち負けは別にして。
〆切りに向かって乗りだすと、私は自分が書こうとしているコトが、既にある作家によって書かれているような気がした。しかも、私には文句の一つもつけようのない形で。
ならば模倣しよう。
本当に飲みたいときには、自分からは誘えないものだ。酒と、それに付きあってくれる仲間を必要としているという自覚もない。
「飲もうよ。ちょっと体動かしたくて」
U子から電話があったときには、だから二つ返事で家を出た。
卓球バーという呼び名は、マスターはダサいと言って疎んじるが、まあそういう店だ。卓球は特別好きでも嫌いでもないが、近所というだけで仲間と何度か訪れていた。
どうせ素人同士、気の利いたテクニックがなくても、来た球をひたすら返していけば勝てる。相手がスマッシュやカットに失敗するのを根気よく待つ。そんなやり方で私はいつも、仲間内ではどちらかと言えば上位につけていた。だけどこの日は、あまりに張りあいがなかったのだろう。
「卓球って気分じゃなかった?」
言われてみればそのとおりだった。ルールだとかラケットだとか、球が跳ね返るということや何かが、大気圏外のように遠い。いつもどおりラケットを当てているはずなのに、球が別の生き物のような動きをする。その生き物に、さして関心を払えない自分がいる。
「だめだね、とうも」
慣例どおり罰ゲームのテキーラを立ったまま飲み干す。カウンターには若い男が一人いるだけで、私たちのゲームを一目見たきり背を向けて、マスターと開幕したばかりのF1グランプリの話をしていた。
「なに、男?」
肯定も否定もしなかったけれども、U子はさっさとカウンターに体を預けて、ハイボールをダブルで頼む。少し迷って、私はズブロッカをロックで頼んだ。
「勘がいいね、相変わらず」
「わかりやすいもの、あなたは」
こんな時間に誘うということは、おそらく彼女のほうで何か話したいことがあったのに違いなかった。霜の降りたグラスに指を這わせて、しばらく間を置いたけれども、切り出したのは私のほうだった。
「二年くらい前に、私がつきあってた男、覚えてる?」
今度はU子が返事を怠った。覚えてるも何も、といったところだろう。
「先週、うちのスタジオに来たんだよね」
「仕事で? だけどスタジオなんて他にいくらもあるでしょう。ヨリ戻したいんじゃないの」
「まさか。戻りようがないもの。向こうもわかってるよ」
「じゃあ、なんで」
「さあ」
彼女の発した問いは、おそらくもっともなのだろう。だけど私には新鮮で、しばらく真面目に考える。
「うちよりマシなスタジオと、私よりマシな技師が、空いてなかったんでしょう」
話してみれば、それだけのことだった。煙草の煙が揺れて、U子が少しこちらを見やるのがわかる。私は目の前のグラスを見ている。
「まあ、それだけなんだけどね」
U子のガラムを一本もらって、慎重に火をつけると、異様なスピードで燃えていく。自分が中毒患者のように吸っていることに、少しして気がついた。
U子は悪酔いするとケンカはするし泣くし物は壊すし、それでも最後は大笑いして帰る、年のわりに古いタイプのミュージシャンだった。そんなU子が結婚するというニュースは、仲間内を沸かせた。人間するときにはするもんだ、と誰かがいい加減に話をまとめれば、世の中の男も捨てたもんじゃない、と誰かがまぜっ返す。そういうざっかけない祝福に、ここひと月ばかり私も加わっていた。
「惚れ込んでたのは知ってたけど。もう終わったもんだとばかり思ってたよ」
「私も」
「だって***さんとつきあってなかったっけ」
「どうなんだろう、あれは、つきあったって言えるのかね」
U子の三つ奥の席に座っている男は、今度は今年の桜の話をしている。目黒川の近くに住んでいるらしい。
二杯目のズブロッカを干して、もうワンセット申し込むと、さっきより大差で負けた。
「ダメじゃん、全然ダメじゃん」
U子はからから笑いながら、ラケットと球を放りだした。私も勢いに任せてショットグラスの底を上げる。
「声が」
私が声を潜めるとU子は注意深げに体を傾けて、その向こうにいる男と私を結ぶ線を遮った。
「似てるの」
すばしこく目を左右させて、言ってる意味がわからない、という風にわずかに首を傾げる。
「あの人の声に聞こえるんだよね、全部とは言わないけど、半分くらいの男の声が。街歩いてても、あの人の声を拾っちゃうんだよね」
「なにそれ。いつから」
「だから、こないだ。あの人が来て、帰ってから。最初は宅急便。一瞬、仕事替えたのかと思った、それかいたずらしにきたのかと思った」
「配達員の声を彼と間違えたってこと? 音響技師なのに?」
U子はガックリと肩を落として、また笑い出した。
「それとも音響技師だから、かね」
「マイクを通して聴く分には平気、どういうわけか。だけど電車に乗ってるときとか、すれ違いざまとか。咳払いとか、笑い声が。いちいち、びっくりするくらい」
「それはきついね」
そのとおりだった。
U子がふいに私の肩を叩いた。
「それで、どうするの」
「別に。どうもしない。どうにもできないし」
「そうかな、そういうもんかね」
「そうだよ、それは」
煙草を二本、灰にした。
「忘れたと思ってたんだけどな」
「そのうちまた忘れるよ」
「そのうちって?」
「すぐだよ、すぐ」
すぐってどれくらいなの、とは聞かなかった。すぐと言ったら、すぐなのだろう。
つられて笑顔を造ると、瞼に心地よい重みを感じた。ふと、U子の結婚を改めて祝福したい気持ちになったけれども、言葉が出てこない。
暖房と煙草でくぐもった空気を追い出すように、マスターが窓を開けると、凍った外気がうっすらと朝焼けていた。いつのまにか、男はいなくなっていた。
友人にメールで作品を送る際、私は自分がある大家の掌編を剽窃したことを書き添えた。
「あまりうまくいったとは言えないものの、やってみていろいろわかったこともあるように思います。当日話をするのを楽しみにしています」
平日の夜に大井町で待ち合わせて、まずはとんかつとビールで乾杯した。当たり障りのない話をしながらロースカツを平らげ、バーに移ってからじゃんけんをした。勝ったのだったか負けたのだったか、私の送ったものから友人の講評を仰ぐことになった。
彼女は作家の名前を二つ挙げた。その一つが、石原慎太郎だった。
「……よくわかったね」
「当たり? 嬉しいな。どの作品かはちょっとわかんなかったけど、もしかしたら、と思って」
私は文庫版『我が人生の時の時』を鞄から取り出して見せた。
「あのね、本当に短い、これと同じくらいのやつ。テニスを卓球にしてみました」
「どれだろう、そんなのあったっけ」
「テニスコートで」と題されたその掌編を、彼女がすぐには思い出せなかったのも無理はない。太平洋の真ん中で迷子になったり、熊や鯨と遭遇したり、「時代と一緒に寝た」と自覚する作家の「人生の時の時」の連なり。私が剽窃したのは、全四十編の中では地味と言って差し支えないものだ。ヨットや猟の話など、私には真似のしようもないことは言うまでもないが。
「友だちとテニスして、酒飲んで、話をする、それだけなんだもの。それが、漂流とか死神の話と同じテンションで書かれてるんだもの」
最初に読んだのは六、七年前だったか。頭上を大きな雲が音もなく過ぎていった、影だけを落として……そんな読後感だった。さあ模倣しようと思って読んでみると、今度は顕微鏡で何か自然界の結晶を覗いたときのような、緻密な美しさが現れた。
「参ったね、正直。どうしてわかったの」
「文体がそれっぽいなと思って。それとサトウさん、好きそうだし」
読書家で考察に優れた彼女ならではのことだろう。このような友人の存在を嬉しく思うと同時に、いまさらのように照れくさい。
「だけど、やってみてなるほどと思ったのは、会話と地の文の区別だね。カギカッコの中では女にふられたって話をしてるんだけど、地の文ではほとんど女が出てこないんだ」
「ちょっと、読ませてくれる?」
私は彼女のために頁を開いて、しばらくの間黙って酒を飲んだ。私が煙草を一本吸い終える前に、ふふふ、と彼女が声を立てた。
「男は半年、女はすぐ、か。アンサーソングみたいになってるわけだね、おもしろい」
「でもねえ、二つばかり小細工した。卓球バーに男の客を置いたのね。これを消すと、かなりスカスカする。書いてて、ちょっと持ち堪えられなかった」
「そう。もう一つは……」
「幻聴というかね。別に聴覚じゃなくてもよかったんだろうけど、何かしないと、未練っぽさが出ないような気がして」
「全体の分量は同じくらいなんだよね?」
私は頷く。
「小細工した分で、石原さんは何を書いているかと思って探してみた。『S』が過去につきあっていた女についての描写があったのね。だから私も『U子』が付き合っていた男を『私』が思い出すって部分を書き足してみたんだけど、どうにもしっくりこなくてヤメちゃった。このあたりでタイムアップ。無謀だったよ。だいたい、時の時って何なのさ」
「ねえ。我が人生の時、だったらまだわかるけど。時の時は、ちょっとねえ」
「『必ず必要』とか『あるものでありはしない』とか、この文体は真似しきれない」
上品な小鼻がぴくぴくしている。彼女流の爆笑だ。
思えばこんな時にこそ俺の人生は飛翔していたのかも知れない……私は作家の手による「あと書きに代えて」を声に出して読みあげた。
「人生の飛翔」
もう一度、呟く。
「そんなことがあるのかね。なさそうだよ、どうも私には」
「わからないよ。後から振りかえると飛翔していた、そういうことがあるのかもしれない」
沈黙が苦にならない。その点でも彼女は貴重な友人だ。
黙ってグラスを傾けながら、私は過去に一度、この作家と遭遇したときのことを思い出していた。もちろん、遭遇したと思っているのは私一人で、向うにしてみれば覚えのないことだろうけれども。
雑誌の仕事で石原慎太郎と立川談志の対談に立ちあったのは、二〇〇六年六月のことだった。薄いジョーゼットのシャツを選んで出かけたということは、そのような気候だったのだろう。銀座六丁目のバーでジンを一杯だけ飲んで、一丁目の「はち巻岡田」に着いたのは定刻の三十分前だった。
「サトウさんは、そこ。談春さんはこちらにお願いします」
先に到着していたF先生が席を割り振っていた。上座は、主客の二人がどう座っても差し支えないように空けてある。
「床の間のない部屋、それだけはお願いしておいたの。二人ともそんなこと気にしないだろうけど。念のため」
現役都知事で作家の石原慎太郎と、国会議員経験もある落語家の立川談志、どちらに床の間を背負わせるか、なるほど難しい問題だ。F先生らしい配慮であり、それだけ神経を使う座だったということでもある。
その甲斐あってか、対談は上首尾に終わった。異次元の感情について、イリュージョン落語について。参議院選挙のこと、大平正芳のこと、田辺茂一や小林秀雄、そして石原裕次郎のこと。時々真剣がかち合うような緊張が走りながらも、掛けあう言葉には親愛がみなぎっていた。
「今日の石原さん、コロッコロしてたね」
料亭の玄関先で深々と頭を下げ、主客二人を見送ると、F先生は会心の笑みで振りかえった。
「おもしろかったね。僕がまとめたいくらいだよ」
同席していた『文藝春秋』の飯窪編集長は、意味ありげな視線を寄こす。こんな豪華な対談の構成を任されて大丈夫? と言いたいのだろう。全然、大丈夫じゃない……飯窪さんには私も大恩があると言ってよいが、このときばかりはイラッとした。ただし、
「速記、頼んでるんでしょ。なるべくそのまま、あまりいじらないほうがいいよ」
この言葉はアドバイスとして胸に留めた。
通常この手の対談・座談会が終わると、数日を経て速記録が上がってくる。構成者はそれを元に、なるべく読みやすく原稿を仕立てる。それが編集部を通じて発話者に届けられ、発話者は著者として事実誤認を訂正し、言い残したことを補足するべく朱字を入れる。その朱字が反映されて、ようやく一本の記事が完成する。
構成者の私が担うのは全体工程の一部だ。できるだけ発話者の真意や気持ちが記事として伝わるように、努めはする。しかしそもそも石原慎太郎と立川談志、後に編集部がつけた見出しによると「日本の文化を過激に支えてきた」二人の「真意や気持ち」を、私が推しはかるなんて、可能よりは不可能に近いのではないか。
無事雑誌となって手元に届くと、真っ先に、どこに朱字が入ったかを確認した。立川談志の朱字にはいくつかの反省を促されたが、石原慎太郎による朱字は、私の予想の範囲外のものだった。
「あなたにはやっぱり、自負があるもの。俺は談志だぞってぇ、自負がある」
この小さい「ぇ」を、私は入れた覚えがない。
「アア、しっかりしろ、ほんとにもう……」
この「アア」も。
「大蔵大臣だった頃の大平さんのところに談志を連れて行って、俺が『よろしくお願いします』って頼んだら、『引き受けた』って言ってくれたよな。それなのにお前、ソファに寝ころがって『何でもいいから金くれ、金ちょうだいよ』って言っただろう」
談志さんが「ソファに寝ころがっていた」とは知らなかった、速記録にも残っていない。なるほど、なるほど……。
私が石原慎太郎という作家に「遭遇」したのは、対談当夜のことではない。自宅兼仕事場のワンルームで誌面を確認し、思わず唸り声を上げた、それから笑ったり泣いたりした、その時のことだ。構成者のただ一人として、あの晩あの場の「真意や気持ち」を仮定し文章に起こした。少なくともこの作家一人は、それをそうと受容し、補強してくれている。そんな実感があった。
対談の構成は何度も経験しているが、そんなことは後にも先にもこれきりだ。
「後からF先生に報告したのね。朱字を入れられて、あんなに嬉しかったことはないって。そしたら『我が都知事の繊細さをわかってくれて、僕も嬉しいです』って。あんときゃそう、都民税払っててよかったと思ったね。ああいう人の下で都民をやるのは悪くないというかね」
友人もあの対談記事を読んでいた。それを思い出そうというように頷いている。
「繊細さか。うん、たしかに繊細だ」
「たとえば私がヨットに乗って遭難して、生きて帰ったとしても、あんなものは書けないよ。それと同じようにね、酒場だとか誰かの葬式で、『時の時』が過ぎていったとしても、それに気がつくことはできないんじゃないかと思うわけ。気がつくことを、繊細と呼ぶのかどうか」
「書くことで、書かれることで、初めて立ち現れるわけだね。『時の時』が」
「うん。だいたい私は、男が女を忘れる、そういう話だと思ってたんだ。だから、女が男を忘れるって話を書こうと思ったときに、思い出したわけだよ。でもどうも勘違いだったね、いまさら気がついた」
「そう? サトウさんのは、あれはあれでアリだと思うよ。別にエラそうに言うつもりはないけど」
「ありがとう。だけど」
講評される側の立場も忘れ、一度閉じた文庫本の頁を、今度は自分のために探った。掌編の後ろから十二行目を人差し指でなぞる。
「今自分が思いがけない友達といるのだな、という気がしていた──この一文が、この作品の柱だったと思うわけ。今となっては、だけどさ」
「つまり『時の時』を自覚したとき……なんだかややこしいけど。柱か、言いたいことはわかるような気もするよ」
「捏造できるものではない。でも、気づかなかったらなかったことになる。両方だね。その二つが揃って……それが才能ってことなのかね」
「わからない。才能ってものは、私にはよくわからない」
「それは私もそうだよ。だけど天才とかね、呼びたくない。そんなつまらないものじゃないと思うんだ」
酔うに任せて、たしかそんなことを喋ったはずだ。
このあと私が講評をぶった彼女の作品については、言うまい。ただ、何らかの形で活字になれば、私は嬉しい。
──『わが人生の時の時』には、「不思議さ」が満ちている──とF先生は説く。船から仲間が落水して「どう考えてもまぎれもない死そのもの」を確認しながら、なぜか身中に「みずみずしい活力のようなもの」が漲ってくる不思議さ。母船を見失って死ぬ目に遭いながら、生還すると他愛のない冗談で笑うことしか出来ない不思議さ。つまり「この世があり、自然があり、海があり、生物がおり、自分が生きているということの、堪え難く、歓喜に満ちた不思議さ。つまり私たちが、人生という時間を持っていることの不思議さそのものを、『わが人生の時の時』は突きつける」、新潮文庫版の解説だ。
私はあの対談の仕事をとおして、文中に小さい「ぇ」を一つ入れるだけで標準語が江戸弁に化けるという「不思議さ」を味わった。言葉によって何かが伝わること。伝わったと思いこんでは満たされ、伝わらなかったと思いこんでは失望するのも、なんでなのかわからない。誰かの書いた言葉が自分の身のうちに入ってきて木魂すること。一つの単語を、一つの文字を、句読点を書いたり消したりして、いったい何が変わるのか。わからなくても、性懲りもなくまた書き直す。一文字の違いを巡って友人と話しあうことも不思議だし、文章を書いてお金をもらうことも、私にとっては不思議なことだ。
石原氏の語る「人生」の相貌に接して、私たちは自分の貧しい「人生」に疑念を抱かざるを得なくなる──とF先生は言う。私は疑念を抱くはるか手前の地点で、読むことと書くことの不思議さにかかりきりになっている。
「一円にもならないつもりで書いた原稿も、こうして何かに使って原稿料に化けることがありますからね」
これを書き終えたら、教えを破ったこととその顛末を報告するつもりだ。
以上、『en-taxi』VOL.27(2009年9月発売号)に掲載された「我が石原慎太郎の慎太郎」を加筆修正のうえ転載しました。大きな変更点は以下のとおり。
1、タイトルの一部変更
もとは「ブルジョワジーの秘かな愉しみ~小金持ちが近代文学を作った」という特集への寄稿だった。石原慎太郎について書くように促したのは福田和也さんで(記事中「F先生」として登場する)、その福田さんは獅子文六について書いていた。
タイトルは変更しなくても問題ないように思ったが、記事のスタンス、筆者の立ち位置をいくらかわかりやすく示す意図で「実録」という冠を付けた。
2、人物の呼称の変更
小説を書いて読み合った友人のことを、初出時は「T」と呼び表していたが、「友人」もしくは「彼女」と改めた。また当時『文藝春秋』編集長だった飯窪氏は、「I編集長」としていたが、実名に改めた。記事中にイニシャル呼びが多くて、少々うるさく感じたこと、飯窪氏については特に名を伏せる必要もないと思われたため。結果的にイニシャルは「F先生」と、架空の人物「U子」のみとなった。
3、最終ブロックの書き直し、および全体のトーンの調整
初出時は石原慎太郎の「処刑の部屋」(新潮文庫版『太陽の季節』所収)の一節を引用し、この作家への自分なりの敬意を述べるという形で結びとしていた。全体の構成を改めて検討した結果、「F先生の教えを破った」という冒頭部分に対応する形で最終ブロックを書き直した。
また、最終ブロックの変更に合わせて全体のトーンを調節した。具体的な例を一つあげると、初出時は石原慎太郎と立川談志の対談について、実際の記事から12行引用していたが、引用ではなく地の文に落とし込む形で省略した。
──そんなわけで転載企画、改稿作業は今回でひと段落。お付き合いくださった方々、どうもありがとうございました。 今回の記事については、2月に読み返した時点ではあまり直す必要を感じなかったものの、結果的には「ここまで手を入れたら、もう別の原稿かも」と思うくらい直すことになりました。
あれこれ手を入れながら考えたこと、思い出したことなど、以下に有料記事として追記します。2000字程度の編集後記、ご興味とお時間のある方は、例によってどうぞ「投げ銭感覚」でご購入ください。