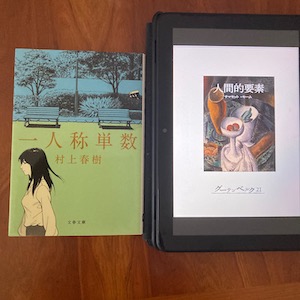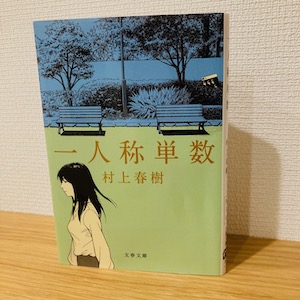
一人称単数の短編小説を、村上春樹さんは過去にいくつも書いている。この短編集に収録された八編には「”僕”もしくは”私”が語る物語」という以外にも、それが小説家・村上春樹である(と思わせる)という共通点があるけど、それだって過去にいくつか例がある。だから最初に読んだときは、どうしてこの短編集に限ってわざわざ『一人称単数』というタイトルにしたのかがわからなかった。今も、わかりはしないけど。
「クリーム」は、同じピアノ教室に通っていた女の子から手の込んだすっぽかしを喰らう話で、表題作「一人称単数」は、バーでたまたま隣あった女性から身に覚えのない吊し上げを喰らう話だ。読むと私はどうしても、ずっと昔に匿名の「誰か」から嫌がらせを受けたときのことを思い出す。高校の美術の授業で描いた絵が切られていたときのことを。
二センチ程度の小さな傷だったから、一つだったら何かのアクシデントだと思った(思い込もうとした)かもしれない。でも自画像とモンドリアンの模写と、二つに同じような切り傷が入っていたのは、悪意によるものだったと認めるしかない。
当時はもちろん頭にきたし、傷ついたし、周囲の人たちに対して疑心暗鬼になったりもした(と思う)。でも結局のところ、どうすることもできなかった。誰かがすごーく私のことを嫌っているんだな、まあ私だって嫌いな人はいるからな、だからといって匿名で嫌がらせをしたりはしないけど……。そんな風に考えて、つまりこれは「私」の問題ではなく、その行為に及んだ「誰か」の問題なんだ、と結論した。
でも、どうなんだろう。本当にそれは「私」の問題じゃなかったのか?
白状すると、中学生のときは下駄箱に入れておいたはずの体育館ばきがゴミ箱から出てきたことがあった。大学の通学に使っていた自転車が二度に渡ってパンクしていたのは、偶然だったとは言い切れない。そんな風に「誰か」から嫌がらせを受けるってことは、何か「私」に問題があったんじゃないの? 今これを読んでいる「誰か」がそう思ったとしても仕方ない、とも思う。
私はそこで彼女に何か反論をするべきだったのだろうか? 「それはいったいどういうことなのですか?」、そう具体的な説明を要求するべきだったのだろうか? 彼女が口にしたことは、私にしてみれば、どう考えても身に覚えのない不当な糾弾だったのだから。
しかしなぜかそれができなかった。どうしてだろう? 私はたぶん恐れていたのだと思う。実際の私でない私が、三年前に「どこかの水辺」で、ある女性──おそらくは私の知らない誰か──に対してなしたおぞましい行為の内容が明らかになることを。そしてまた、私の中にある私自身のあずかり知らない何かが、彼女によって目に見える場所に引きずり出されるかもしれないことを。(「一人称単数」より)
自己同一性という概念があるけれど、この短編集のテーマはもしかすると自己”非”同一性のようなものかもしれないなあ、と思ってみたりする。「私」の不確かさ。「私」に主体性があるとすれば、「誰か」にも主体性があること。その歪みに、何か大事なものがある、とでもいうような。
念のため、すっぽかしとか吊し上げを喰らう話ばかりではない。早逝したサックス奏者が夢に出てきて、”僕”のためだけに特別な一曲を吹いてくれる、という楽しい話もある(チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ)。……夢といえば、高校を卒業する間際にこんな夢を見た。私は私の描いた絵をカッターで切り付けた「誰か」を走って追いかける。校舎の突き当たりまで追い詰めて、罵倒しながらパイプ椅子でメッタメタのボコボコにする夢だ。私としてはそんな凶暴な復讐を望んではいなかった、というかその頃にはほとんど忘れたように日常生活を送っていたけれども。目覚めたときの爽快感は忘れられない。
この短編集で私が一番好きなのは「神宮球場とスワローズと村上春樹」が登場する随筆風の物語だ(”ヤクルト・スワローズ詩集”)。”僕”が膨大な数の負け試合を目撃し続けることで「今日もまた負けた」という世界のあり方に自分の体を慣らしていったように、私は匿名の誰かの嫌がらせを何度か受けることで「誰かが私を嫌っていたとしても仕方ないではないか」という気の持ちようを身につけたんだと思う。それは決して楽しい経験ではなかったけれども、今ではすっかり私の一部になっている。
あのときの「誰か」がいつかどこかでこれを読むかもしれない、その可能性はゼロではないから、一応書いておく。私の知らない「私」がその「誰か」を傷つけたんだと思うし、それに夢でメッタメタのボコボコにしたから、私はもう怒ってないし傷ついてもいないよ。